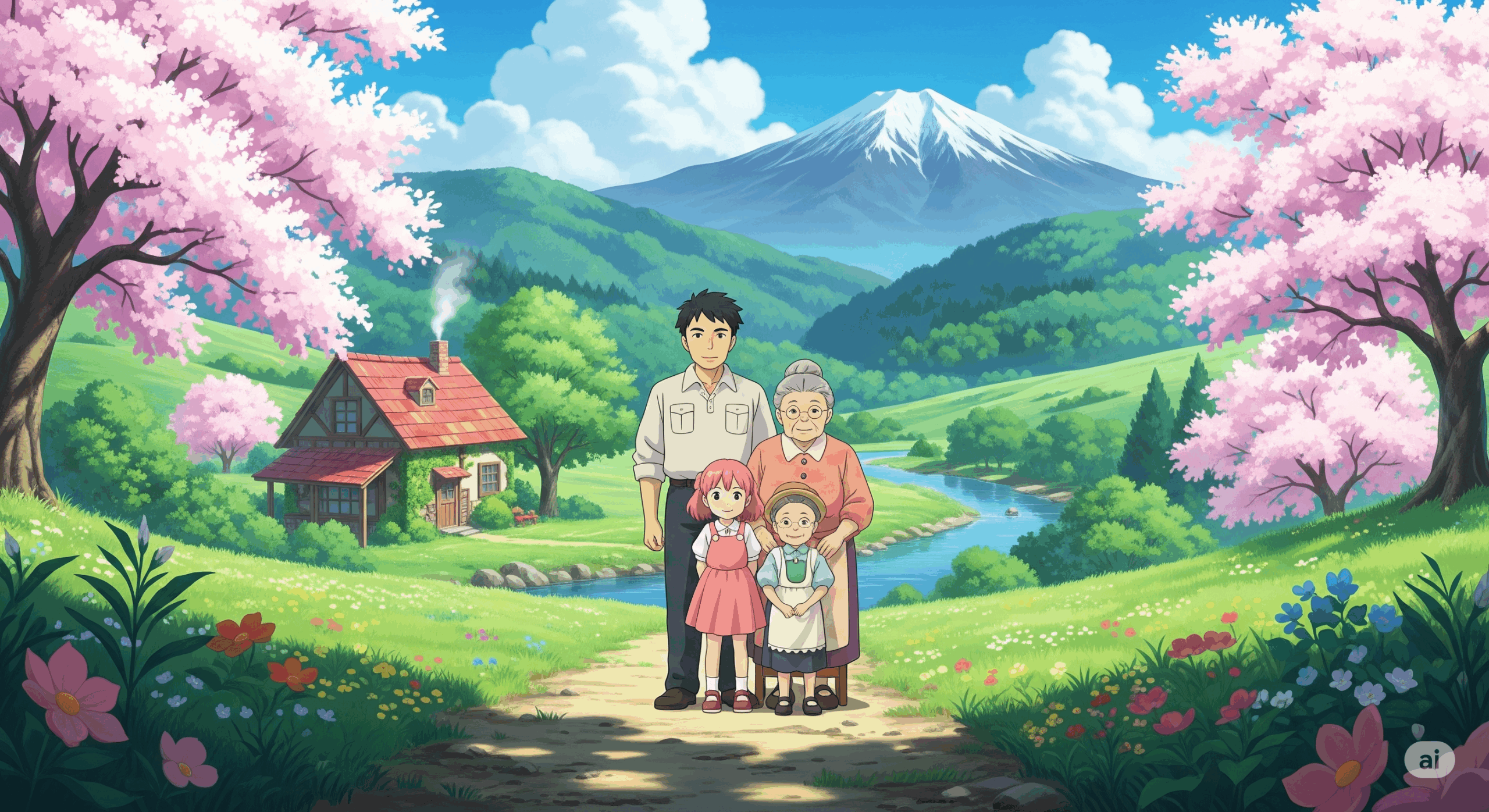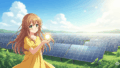扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、所得金額から一定の金額を差し引くことができる所得控除の一つです。この制度は、扶養親族がいる納税者の税負担を軽減し、国民の生活を安定させることを目的としています。扶養控除が適用されると、課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の納税額が少なくなります。
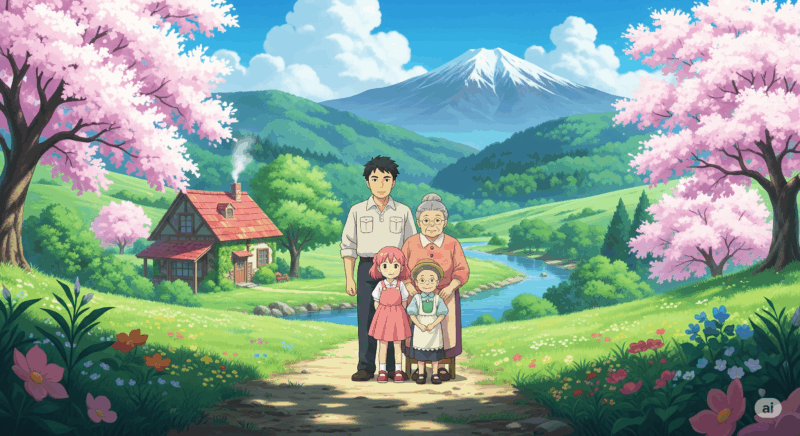
扶養控除とは
1. 扶養控除の基本的な仕組みと目的
扶養控除は、所得税法第84条に規定されており、扶養親族の年齢や同居の有無、その他の条件によって控除額が異なります。この制度の根底には、「家族を養う負担を負っている納税者には、その負担に応じて税制上の優遇措置を与えるべきである」という考え方があります。
具体的には、納税者の所得から一定額が控除されることで、課税対象となる所得額が減ります。所得税は累進課税制度であるため、課税所得が減れば適用される税率も下がり、税額が大きく軽減される可能性があります。
2. 扶養控除の対象となる扶養親族の要件
扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族が以下のすべての要件を満たす必要があります。
1. 配偶者以外の親族であること 扶養親族は、納税者の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である必要があります。また、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から養護を委託された老人(養護老人ホームに入居しているなど)も対象に含まれます。
2. 生計を一にしていること 「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを意味しません。同じ家計で生活している、つまり生活費を共有している状態を指します。例えば、単身赴任中の夫が実家に住む妻や子供に生活費を送金している場合や、大学に通うために一人暮らしをしている子供に仕送りをしている場合なども「生計を一にする」とみなされます。別居していても、常に生活費や学資金、療養費などを送金している場合は該当します。
3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること 扶養親族の年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。給与所得者の場合、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額55万円を差し引くと所得金額が48万円以下になります。これは、いわゆる「103万円の壁」として知られています。
- 給与所得者の場合: 給与収入 - 給与所得控除(最低55万円) ≦ 48万円
- 例:給与収入103万円の場合、103万円 – 55万円 = 48万円となり、要件を満たします。
- 年金所得者の場合: 公的年金等収入 - 公的年金等控除額 ≦ 48万円
- 年齢によって公的年金等控除額が異なります。
- 事業所得者の場合: 事業収入 - 必要経費 ≦ 48万円
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと これは、個人事業主の事業を手伝っている家族が、給与を受け取っている場合や、事業専従者と認められている場合には、扶養親族とはみなされないというルールです。事業専従者は、別途「専従者給与」として経費計上されるため、扶養控除の対象からは外れます。
3. 扶養控除の種類と控除額
扶養控除は、扶養親族の年齢によって控除額が異なります。これは、年齢によって生計を支える上での負担が異なるためです。
1. 一般の扶養親族
- 対象者: その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族
- 控除額: 38万円
2. 特定扶養親族
- 対象者: その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族
- 控除額: 63万円
- 目的: 主に大学や専門学校など、教育費の負担が大きい時期の子供を扶養している納税者に対する優遇措置です。
3. 老人扶養親族
- 対象者: その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の扶養親族
- 控除額:
- 同居老親等: 58万円(納税者または配偶者の直系尊属で、常に納税者または配偶者と生計を一にし、かつ同居している場合)
- 「同居」は、病気の治療のため入院している場合も、治療が終わり次第帰宅できると認められる場合には同居とみなされます。しかし、老人ホーム等に入所している場合は同居とはみなされません。
- その他: 48万円(上記以外の老人扶養親族)
- 同居老親等: 58万円(納税者または配偶者の直系尊属で、常に納税者または配偶者と生計を一にし、かつ同居している場合)
4. 住民税における扶養控除額 所得税とは異なり、住民税における扶養控除額も定められています。通常、所得税の控除額よりも住民税の控除額の方が低く設定されています。
- 一般の扶養親族: 33万円
- 特定扶養親族: 45万円
- 老人扶養親族:
- 同居老親等:45万円
- その他:38万円
4. 扶養控除の適用対象外となるケース
以下のケースでは、扶養控除が適用されません。
- 15歳以下の子供(年少扶養親族): 2011年度(平成23年度)の税制改正により、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い、15歳以下の扶養親族に対する扶養控除は廃止されました。これは、子ども手当が支給されることで、子育て支援は別途行われるという考え方に基づいています。
- 配偶者: 配偶者は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となります。
- 扶養親族の合計所得金額が48万円を超える場合: 上記「2.」で説明したとおりです。
- 青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者: 上記「2.」で説明したとおりです。
5. 扶養控除の手続き方法
扶養控除の適用を受けるためには、年末調整または確定申告の手続きが必要です。
1. 年末調整の場合 会社員や公務員など、給与所得者の場合は、勤務先が行う年末調整で手続きを行います。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出: 毎年、会社から配布されるこの書類に、扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、所得の見込みなどを記入して提出します。
- 年の途中で扶養親族に異動があった場合: 結婚、出産、扶養親族の所得状況の変化など、年の途中で扶養親族に変動があった場合は、速やかに勤務先に申し出て「扶養控除等申告書」を再提出する必要があります。
2. 確定申告の場合 個人事業主や、年間の所得が2,000万円を超える給与所得者、または年末調整で扶養控除の適用を忘れた場合などは、ご自身で確定申告を行う必要があります。
- 確定申告書の作成: 国税庁のウェブサイトや確定申告ソフトを利用して、確定申告書を作成します。
- 必要事項の記入: 扶養控除に関する欄に、扶養親族の情報を正確に記入します。
- 提出: 作成した確定申告書を税務署に提出します(e-Taxによる電子申告が便利です)。
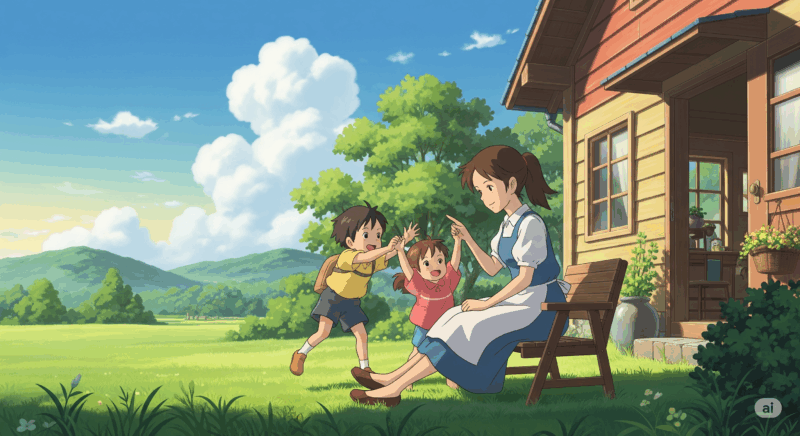
6. 扶養控除に関する注意点とポイント
1. 扶養控除と配偶者控除・配偶者特別控除の違い 扶養控除は配偶者以外の親族が対象であるのに対し、配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者が対象です。これらの控除は併用できないため、それぞれ個別に要件を確認し、適切な控除を適用する必要があります。
2. 複数人が同じ扶養親族を控除することの禁止 一人の扶養親族に対して、複数の納税者が扶養控除を適用することはできません。例えば、夫婦共働きの場合、子供はどちらか一方の納税者のみが扶養控除の対象とすることができます。一般的には、所得の高い方が扶養控除を適用した方が、節税効果は大きくなります。
3. 年の途中で扶養親族の状況が変わった場合 扶養親族の年齢が16歳以上になった、所得が増えて48万円を超えた、海外に転居したなど、年の途中で扶養親族の状況が変わった場合は、控除対象から外れる可能性があります。年末調整や確定申告の際に、最新の情報に基づいて申告を行うことが重要です。
4. 海外居住の扶養親族に関する取り扱い 2023年1月1日以降、海外に居住する扶養親族(非居住者である親族)については、送金関係書類の提出義務化や、年齢による要件の厳格化が行われました。
- 16歳以上30歳未満の扶養親族: 留学、仕事など、特定の理由がある場合に限って扶養控除の対象となります。
- 留学により日本を離れている者
- 障害者
- 納税義務者から38万円以上の生活費または教育費の送金を受けている者
- 30歳以上70歳未満の扶養親族: 原則として扶養控除の対象外となります。
- 70歳以上の扶養親族: 引き続き扶養控除の対象となります。
- 送金関係書類の提出: 海外に居住する扶養親族について扶養控除を適用する場合、送金していることを証明する「送金関係書類」を提出または提示する必要があります。これは、不正な申告を防ぐための措置です。
5. 扶養控除と医療費控除などの併用 扶養控除は、医療費控除や生命保険料控除など、他の所得控除と併用することができます。それぞれの控除の要件を満たしていれば、複数の控除を適用することで、より税負担を軽減することが可能です。
6. 所得税と住民税への影響 扶養控除は、所得税だけでなく住民税にも影響します。所得税の扶養控除額と住民税の扶養控除額は異なりますが、どちらも税負担の軽減に繋がります。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、所得税の確定申告(または年末調整)の内容が翌年度の住民税に反映されます。
7. まとめ
扶養控除は、納税者が扶養親族を持つことによる経済的負担を考慮し、税制を通じてその負担を軽減する目的で設けられた重要な制度です。適用されるためには、扶養親族の範囲、生計の一致、所得制限などの要件を満たす必要があります。また、扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なり、特に特定扶養親族や老人扶養親族には手厚い控除が用意されています。
年末調整や確定申告の際には、これらの要件を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、税負担の軽減に繋がります。特に、海外に居住する扶養親族については、2023年からの制度改正に注意が必要です。ご自身の家族構成や所得状況に合わせて、最大限の控除を受けられるよう、不明な点があれば税務署や税理士に相談することをお勧めします。