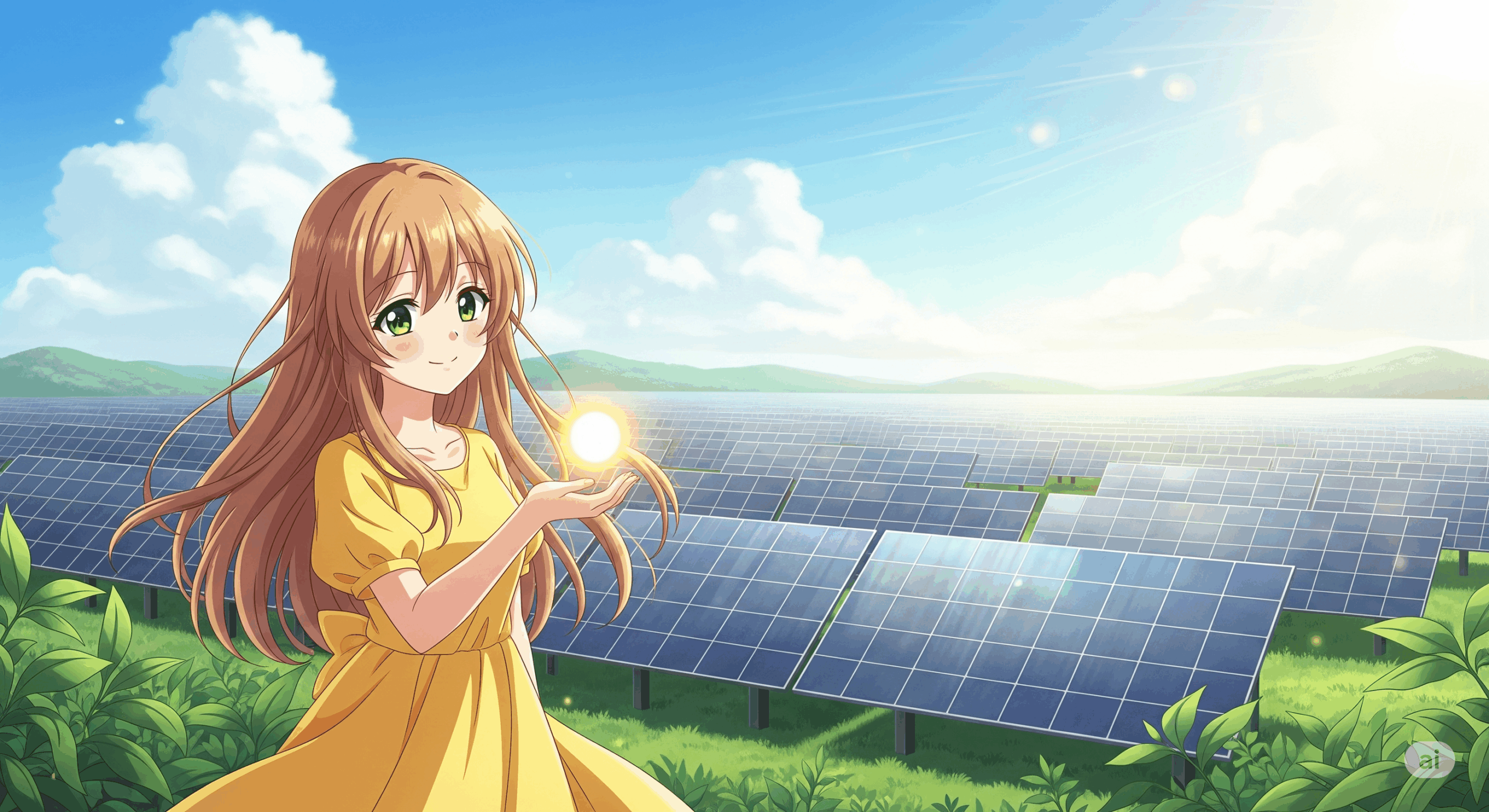10年目を迎える太陽光発電システムを所有されている方にとって、その後の運用は重要な検討事項となります。FIT制度による固定価格買取期間が終了し、売電価格が大幅に低下する中で、これまでの投資を最大限に活かし、さらに利益を生み出すための戦略的な選択が求められます。
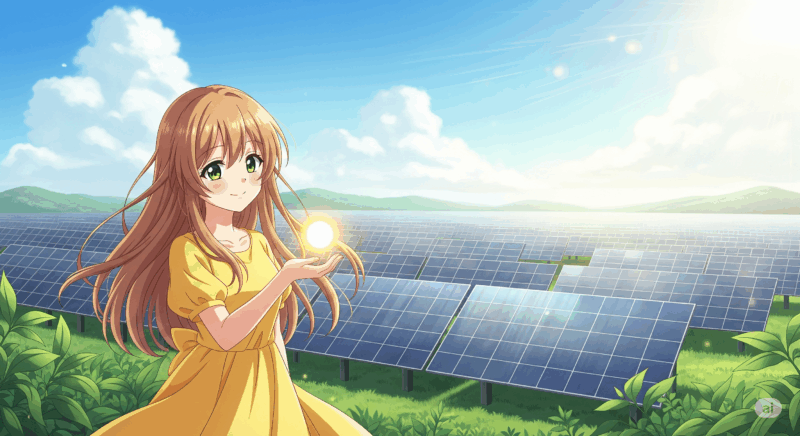
FIT制度終了後の太陽光発電システムの現状と課題
日本の太陽光発電市場は、2009年に開始されたFIT(Feed-in Tariff)制度によって大きく成長しました。この制度は、再生可能エネルギーの導入を促進するため、太陽光発電で発電された電力を電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを義務付けるものです。特に2012年7月に導入された高額な買取価格は、多くの家庭や企業が太陽光発電システムの導入に踏み切る大きな要因となりました。
しかし、FIT制度には期間が設けられており、住宅用太陽光発電の多くは10年間、産業用太陽光発電は20年間と定められています。FIT制度開始から10年が経過した現在、2019年以降、順次、固定価格買取期間が終了する「卒FIT」を迎える太陽光発電システムが増加しています。
卒FITがもたらす課題:
- 売電価格の大幅な低下: FIT制度が終了すると、これまでの高額な買取価格から、電力会社が提示する市場価格に連動した、はるかに低い価格での売電となります。これは、固定価格買取期間中の売電収入を前提とした投資回収計画に大きな影響を与えます。
- システムの老朽化: 10年間稼働したシステムは、パワコン(パワーコンディショナ)などの機器の経年劣化が進み、故障のリスクが高まります。メンテナンスや交換費用が発生する可能性があります。
- 保証期間の終了: 多くのメーカー保証は10年間であるため、卒FIT後には保証期間が終了し、故障時の修理費用が全額自己負担となる可能性があります。
このような課題に直面する中で、太陽光発電システムの所有者は、売電収入の減少、メンテナンスコストの増加、そしてシステム全体の寿命といった複合的な要素を考慮し、10年目以降の最適な選択肢を見つける必要があります。
10年目以降の主要な選択肢
FIT制度終了後、太陽光発電システムの所有者が取り得る選択肢は、大きく分けて以下の4つに集約されます。
1. 売電の継続(相対・自由契約)
これは最もシンプルな選択肢であり、FIT制度終了後も、これまでの電力会社、あるいは別の電力会社と個別に契約を結び、余剰電力を売電し続ける方法です。
メリット:
- 手続きが比較的容易: 特別な機器の導入や大幅なシステムの変更は不要です。
- 初期投資が不要: 新たな設備投資は基本的に発生しません。
- 継続的な収益: 少額ながらも売電収入を得られます。
デメリット:
- 売電価格が非常に低い: FIT制度中の数分の一程度になることがほとんどで、十分な収益は期待できません。現在の市場価格では、家庭用電力量料金の半分以下となるケースが一般的です。
- 収益性の低下: 売電収入だけでは、初期投資の回収や今後のメンテナンス費用を賄うことが困難になる可能性があります。
- 市場価格の変動リスク: 売電価格は市場の電力需給によって変動するため、不安定な収入源となる可能性があります。
具体的な選択肢:
- 大手電力会社の買取プラン: 各電力会社が「卒FIT」向けの買取プランを提供しています。多くは、独自のポイント付与や、電気料金との相殺といったインセンティブがあります。
- 新電力会社の買取プラン: 新電力の中には、大手電力会社よりも高めの買取価格を設定しているところや、特定のサービスと組み合わせたプランを提供しているところもあります。
検討すべきポイント:
- 買取価格の比較: 複数の電力会社の買取価格を比較検討し、最も有利な条件を選ぶことが重要です。
- 契約条件の確認: 契約期間、解約条件、手数料などを事前に確認しましょう。
- 自家消費とのバランス: 売電価格が低い場合、売電を継続するよりも、自家消費を増やす方が経済合理性が高まる可能性があります。
2. 自家消費の最大化(蓄電池導入・エコキュート連携など)
売電価格が大幅に低下する中で、発電した電力を売るのではなく、自分で消費する「自家消費」に舵を切ることは、経済合理性の高い選択肢となります。特に、日中に太陽光発電で発電した電力を、夜間や悪天候時に利用するために蓄電池を導入することは、自家消費を最大化する上で非常に有効な手段です。
メリット:
- 電気代の削減: 電力会社からの買電量を減らすことで、電気代を大幅に削減できます。特に電気料金が高い時間帯の買電を抑制できるため、経済的なメリットが大きいです。
- 停電時の備え: 蓄電池があれば、災害などによる停電時にも、蓄えた電力で家電製品を使用できるため、非常用電源として機能します。
- 環境貢献: 自家消費は、再生可能エネルギーの地産地消を促進し、電力系統への負担を軽減するため、環境負荷の低減に貢献します。
- 経済的なメリットの向上: 今後の電気料金上昇リスクをヘッジできます。電力会社から電気を買うよりも、自家消費する方がメリットが大きくなる傾向にあります。
デメリット:
- 初期投資が必要: 蓄電池の導入には、数十万円から数百万円の費用がかかります。導入費用と、将来的な電気代削減効果を慎重に比較検討する必要があります。
- 設置スペースの確保: 蓄電池はそれなりの大きさがあるため、設置スペースの確保が必要です。
- 劣化と寿命: 蓄電池にも寿命があり、10年程度で交換が必要になる可能性があります。
自家消費最大化のための具体策:
- 蓄電池の導入: 最も効果的な自家消費促進策です。太陽光発電で発電した余剰電力を蓄電池に貯め、夜間や早朝、悪天候時など、太陽光発電が稼働しない時間帯に利用します。AIが搭載された蓄電池であれば、電力使用パターンを学習し、最適な充放電を自動で行うことも可能です。
- エコキュートなど給湯器との連携: 太陽光発電の余剰電力を利用して、エコキュートや電気温水器で沸き上げを行うことで、電気代を削減できます。
- EV(電気自動車)/PHEV(プラグインハイブリッド自動車)への充電: EV/PHEVを所有している場合、太陽光発電の余剰電力で充電することで、ガソリン代の節約につながります。V2H(Vehicle to Home)システムを導入すれば、EV/PHEVに蓄えられた電力を家庭で利用することも可能です。
- スマート家電との連携: HEMS(Home Energy Management System)を導入し、太陽光発電の発電量や電力消費状況を「見える化」することで、効率的なエネルギー利用を促進できます。また、スマート家電と連携することで、電力消費を最適化することも可能です。
検討すべきポイント:
- 経済性: 蓄電池の導入費用、補助金、電気代削減効果、売電収入の損失などを総合的に評価し、投資回収期間を算出することが重要です。
- 蓄電池の容量: 家庭の電力使用量やライフスタイルに合わせて、適切な容量の蓄電池を選ぶことが重要です。
- 設置場所と工事: 蓄電池の設置場所の確保や、専門業者による工事が必要となります。
- V2Hの導入: EV/PHEVを所有している場合は、V2Hシステムの導入も検討することで、より自家消費のメリットを享受できます。
3. 売電と自家消費の組み合わせ(ハイブリッド)
多くの家庭にとって、売電と自家消費のどちらか一方に特化するのではなく、両者をバランス良く組み合わせる「ハイブリッド」が最も現実的で合理的な選択肢となるでしょう。発電した電力の一部は自家消費に回し、余剰となった電力は売電することで、安定した電気料金削減と、わずかながらも売電収入を確保できます。
メリット:
- リスクの分散: 売電価格の変動リスクと、蓄電池導入に伴う初期投資リスクの両方を分散できます。
- 柔軟な運用: 電力価格や家庭の電力需要の変化に合わせて、自家消費と売電のバランスを調整できます。
- 経済的メリットの最大化: 売電価格が低い時間帯は自家消費を優先し、売電価格が高い時間帯は売電を優先するなど、効率的なエネルギー利用が可能です。
デメリット:
- システム設計の複雑さ: 自家消費と売電のバランスを最適化するには、ある程度の知識や計画が必要です。
- 機器選択の複雑さ: 自家消費を促進するための蓄電池やHEMSなどの導入も検討するため、機器選定の幅が広がります。
具体的な運用例:
- 日中の余剰電力の売電: 日中の太陽光発電の発電量が多く、家庭での電力消費が少ない時間帯は、余剰電力を電力会社に売電します。
- 夜間・早朝の蓄電池からの供給: 夜間や早朝など、太陽光発電が稼働しない時間帯や、発電量が少ない時間帯は、蓄電池に貯めた電力で家庭の電力をまかないます。
- 電気料金のピークカット: 電気料金が最も高くなる時間帯(ピークタイム)には、蓄電池から電力を供給することで、電力会社からの買電を抑え、電気代を削減します。
検討すべきポイント:
- 電力プランの見直し: 自家消費と売電のバランスに合わせて、最適な電力会社の料金プランを選択することが重要です。夜間割引のあるプランや、時間帯別料金プランなどを検討しましょう。
- HEMSの活用: HEMSを導入することで、電力の使用状況や発電量をリアルタイムで把握し、最適なエネルギー管理を行うことができます。
- 蓄電池の適切な容量選択: 自家消費に回す電力と、売電に回す電力のバランスを考慮し、適切な容量の蓄電池を選ぶことが重要です。
4. システムの撤去・売却
FIT期間が終了し、売電収入が大幅に減少することで、今後のメンテナンス費用や故障リスクを考慮し、太陽光発電システムを撤去するという選択肢も考えられます。また、中古市場での売却や、設備の再利用も選択肢となり得ます。
メリット:
- メンテナンス費用や故障リスクの回避: 今後のメンテナンス費用や、経年劣化による故障のリスクから解放されます。
- 屋根の利用自由度: 屋根の防水工事やリフォームを検討する際に、制約がなくなります。
- 初期費用の回収: 中古市場で売却することで、一部でも初期費用を回収できる可能性があります。
デメリット:
- 撤去費用が発生: 太陽光発電システムの撤去には、数万円から数十万円の費用がかかります。
- 売電収入の消滅: 当然ながら、売電収入は一切なくなります。
- 環境貢献の機会損失: 再生可能エネルギーの利用をやめることになります。
- リユース・リサイクルコスト: パネルなどの廃棄には、リサイクル費用がかかる場合があります。
具体的な選択肢:
- 専門業者による撤去: 太陽光発電システムの撤去を専門に行う業者に依頼します。
- 中古市場での売却: まだ使用可能なシステムであれば、中古市場や専門業者に売却できる可能性があります。ただし、買い取り価格は非常に低くなることが予想されます。
- パネルのリサイクル: 撤去した太陽光パネルは、適切にリサイクルされる必要があります。リサイクル費用や方法について、事前に確認しておくことが重要です。
検討すべきポイント:
- 撤去費用と売却価格の比較: 撤去にかかる費用と、売却によって得られる収入を比較し、経済的なメリットがあるかどうかを判断します。
- システムの現状: システムの状態や年数、メーカー、型番などによって、売却価格は大きく異なります。
- 環境への配慮: 撤去する場合には、パネルのリサイクルなど、環境に配慮した適切な処理を行う業者を選ぶことが重要です。
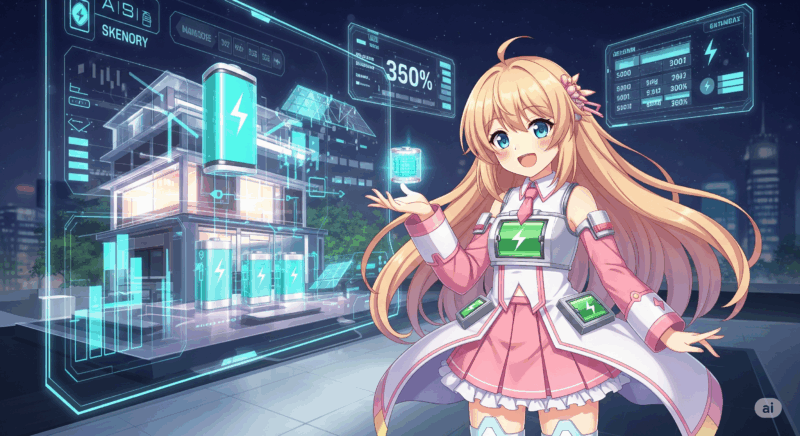
選択肢を検討する上での重要ポイント
10年目以降の太陽光発電システムの選択肢を決定する際には、以下の要素を総合的に考慮することが不可欠です。
1. 経済性
最も重要な要素の一つです。
- 現在の電気使用量と料金: 家庭の電気使用量や、現在の電力会社の料金プランを詳細に把握しましょう。夜間の電気使用量が多い家庭は蓄電池のメリットが大きいです。
- 売電価格と自家消費による電気代削減効果の比較: FIT制度終了後の売電価格と、自家消費によって削減できる電気代を具体的に試算し、どちらが経済的に有利かを比較します。
- 初期費用と投資回収期間: 蓄電池導入などの初期費用と、それによって得られる経済的メリット(電気代削減効果など)を考慮し、投資回収期間を算出します。補助金制度の有無も確認しましょう。
- メンテナンス費用と故障リスク: 今後のメンテナンス費用(パワコン交換など)や、経年劣化による故障リスクを考慮に入れます。メーカー保証が切れている場合は、特に注意が必要です。
- 将来の電気料金の動向: 今後、電気料金が上昇する可能性が高いことを考慮すると、自家消費のメリットはさらに大きくなる可能性があります。
2. ライフスタイルと価値観
家庭の電力使用パターンや、環境への意識も選択に影響を与えます。
- 日中の在宅時間: 日中に家にいる時間が長く、エアコンや照明を多く使う家庭は、自家消費のメリットを享受しやすいです。
- 停電への備え: 災害への意識が高い方や、非常時の電力確保を重視する方は、蓄電池導入の優先順位が高くなります。
- 環境意識: 再生可能エネルギーの利用を通じて環境貢献を続けたいと考える方は、自家消費や売電の継続を選ぶ可能性が高いでしょう。
3. 補助金制度の活用
国や地方自治体は、再生可能エネルギー導入を促進するため、様々な補助金制度を設けています。特に、蓄電池の導入には高額な補助金が用意されている場合があります。
- 国による補助金: 経済産業省や環境省などが、定置型蓄電池導入支援事業などの補助金を提供している場合があります。
- 地方自治体による補助金: 各地方自治体も、独自に太陽光発電システムや蓄電池の導入に対する補助金制度を設けていることがあります。
- 補助金情報の収集: 居住地の自治体のウェブサイトや、関連団体の情報を定期的に確認し、利用可能な補助金を積極的に活用しましょう。補助金は予算に限りがあり、期間が限定されていることも多いため、早めの情報収集と申請が重要です。
4. システムの状態とメンテナンス 🛠️🩺
10年間使用したシステムは、経年劣化が進んでいます。
- パワコンの寿命: パワーコンディショナの寿命は一般的に10年程度と言われています。故障している場合は交換が必要となり、費用が発生します。
- パネルの状態: パネルに目立った損傷や劣化がないか確認しましょう。発電効率が著しく低下している場合は、交換を検討する必要があるかもしれません。
- 定期的な点検とメンテナンス: 今後の安定稼働のためには、専門業者による定期的な点検やメンテナンスが不可欠です。故障の早期発見や、発電効率の維持につながります。
将来を見据えた選択 展望
太陽光発電システムの10年目以降の選択は、単なる経済的な判断だけでなく、持続可能な社会への貢献、エネルギー自給自足の意識の高まりなど、多様な側面から検討されるべきです。
スマートグリッドとVPPへの参加
将来的には、より高度なエネルギーマネジメントシステムへの参加も選択肢となり得ます。
- スマートグリッド: IT技術を活用して電力の供給と需要を最適化する次世代電力網です。太陽光発電システムがスマートグリッドと連携することで、より効率的なエネルギー利用が可能になります。
- VPP(バーチャルパワープラント): 複数の分散型電源(太陽光発電、蓄電池など)を統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させるシステムです。VPPに参加することで、電力の需給調整に貢献し、新たな収益機会を得られる可能性があります。
RE100と企業の取り組み
企業においては、RE100(事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ)への貢献という観点からも、太陽光発電システムの継続利用は重要です。自家消費を最大化し、再生可能エネルギー比率を高めることで、企業のCSR(企業の社会的責任)を果たすことができます。
地域コミュニティとの連携
地域全体で再生可能エネルギーの地産地消を進める動きも活発化しています。
- 地域マイクログリッド: 地域内で電力を自給自足し、災害時にも電力供給を継続できるようなシステムです。太陽光発電システムが地域マイクログリッドの一員となることで、地域のレジリエンス向上に貢献できます。
- 地域新電力との連携: 地域に根差した新電力会社と連携し、地域内で発電された電力を地域内で消費する仕組みに参加することも考えられます。
まとめ
太陽光発電システムの10年目以降の選択は、オーナーそれぞれの状況や目標によって異なります。最も重要なのは、FIT制度終了後の売電価格の大幅な低下という現実を受け止め、ご自身の電力使用状況、経済状況、そして今後のライフプランを総合的に考慮し、最適な選択を行うことです。
売電の継続、自家消費の最大化、ハイブリッド運用、そしてシステムの撤去・売却という4つの主要な選択肢の中から、それぞれのメリット・デメリット、経済性、補助金制度の活用、そして将来的な展望を踏まえて、後悔のない賢明な意思決定を行うことが、これまでの投資を最大限に活かし、さらにその先の利益を追求するための鍵となります。専門家のアドバイスも積極的に活用し、ご自身にとって最善の道を見つけてください。
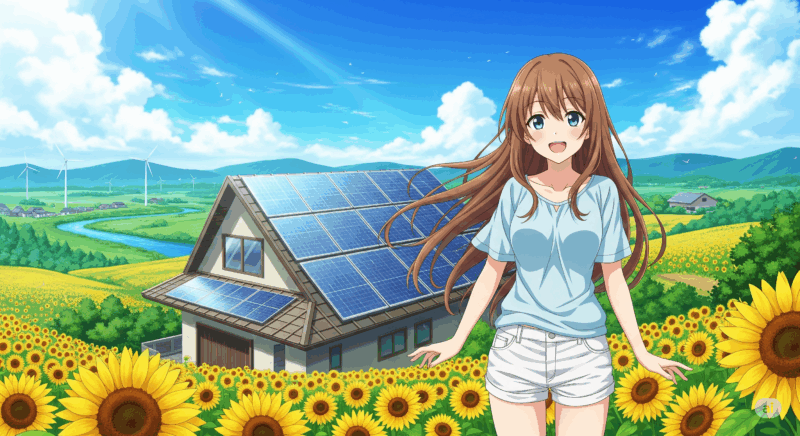
1. 売電の継続(相対・自由契約)を選択する場合
FIT期間終了後は、電力会社が設定する「卒FIT買取プラン」を利用することになります。大手電力会社だけでなく、新電力会社も様々なプランを提供しており、価格やサービス内容が異なります。
主要な電力会社・新電力会社(例)
- 大手電力会社(地域電力会社):
- 北海道電力
- 東北電力
- 東京電力エナジーパートナー
- 中部電力ミライズ
- 北陸電力
- 関西電力
- 中国電力
- 四国電力
- 九州電力
- 沖縄電力
- 新電力会社:
- Q.ENESTでんき (株式会社エネチェンジ): 比較的高めの買取価格を提示している場合があります。
- エネクスライフサービス (伊藤忠エネクスグループ): 「卒FITでんきプラス」など、自社の電気とセットにすることで買取価格が上がるプランを提供しています。
- idemitsuでんき (出光興産): 自社の電気とセットにすることで買取価格が上がるプランを提供しています。
- エバーグリーン・リテイリング: 電気契約者向けに高めの買取プランを提供している場合があります。
- 楽天でんき: 楽天ポイントとの連携など、独自のサービスを提供しています。
- JAでんき (全農エネルギー): JAグループの組合員向けにサービスを提供しています。
- HTBエナジー: 旅行などと連携したユニークなプランを提供していることもあります。
- looopでんき: 基本料金0円プランなど、特徴的な料金体系で知られています。
- 地域新電力(例: みやまスマートエネルギー、いこま市民パワー、おいでんエネルギーなど): 特定の地域に特化し、地産地消を推進する形で買取サービスを提供している場合があります。
選定のポイント:
- 買取価格: 各社の提示する買取価格を比較検討します。地域によって価格が異なります。
- 電気料金とのセット割引: ご自身の電力使用状況に合わせて、電気料金とセットで契約した場合のメリットを比較します。
- 付加サービス: ポイント付与、提携サービスとの連携など、付加価値にも注目します。
- 契約期間や解約条件: 契約期間の縛りや、解約時の手数料などを確認します。
2. 自家消費の最大化(蓄電池導入・エコキュート連携など)を選択する場合
蓄電池やHEMS(Home Energy Management System)、V2H(Vehicle to Home)などの設備導入に関わる企業が選択肢となります。
蓄電池・HEMS・V2Hの販売・設置・施工業者(例)
- 大手家電量販店:
- ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラなど
- 多様なメーカーの蓄電池を取り扱っており、独自のキャンペーンやポイント還元などがある場合があります。
- 設置工事も請け負うことが多いですが、提携業者への委託の場合もあります。
- 住宅メーカー・工務店:
- 新築時に太陽光発電を導入したハウスメーカーや、地元の工務店に相談するのも良いでしょう。
- 住宅全体のエネルギーマネジメントを含めた提案を受けられる場合があります。
- 例: 旭化成ホームズ(ヘーベルハウスオーナー向けに卒FIT買取サービスも提供)など
- 太陽光発電システム販売・施工専門業者:
- これまで太陽光発電システムの設置を行ってきた専門業者に相談するのが一般的です。
- 蓄電池の導入実績も豊富で、システムの連携や最適な提案を期待できます。
- 例: 株式会社サンフィールド、株式会社ハウスプロデュース、鈴与商事など、多くの地域密着型や全国展開の業者があります。
- 「タイナビ蓄電池」のような一括見積もりサイトを利用して、複数の業者から見積もりを取ることも可能です。
- V2Hシステムメーカー・販売・設置業者:
- ニチコン: V2Hシステムの主要メーカーであり、設置業者も多く存在します。
- デンソー: V2Hシステムを取り扱っています。
- EV/PHEVを販売している自動車メーカーの関連企業や、EV充電設備専門の業者なども選択肢となります。
選定のポイント:
- 実績と信頼性: 蓄電池やV2Hの設置実績が豊富で、信頼できる業者を選びましょう。
- 製品ラインナップ: ご自身のニーズに合った容量や機能の蓄電池を提案してくれるか確認します。
- 保証期間とアフターサービス: 設置後の保証期間や、トラブル時のサポート体制を確認します。
- 補助金申請サポート: 補助金制度の情報を詳しく、申請手続きをサポートしてくれる業者を選ぶとスムーズです。
- 見積もり内容の明確さ: 工事費用、機器費用、諸費用など、見積もりの内訳が明確であることを確認します。
3. システムの撤去・売却を選択する場合
システムの撤去には専門的な知識と技術が必要です。また、使用可能なシステムであれば、中古市場での売却も検討できます。
太陽光発電システム撤去・処分業者(例)
- 太陽光発電システム販売・施工専門業者:
- 新規設置だけでなく、撤去工事も請け負う業者が多いです。
- システムの構造を理解しているため、安全かつ効率的な撤去が期待できます。
- パネルのリサイクルについても相談できる場合があります。
- 解体業者・産業廃棄物処理業者:
- 一般的な解体工事を行う業者や、産業廃棄物処理の許可を持つ業者も、太陽光発電システムの撤去・処分に対応している場合があります。
- 複数の業者から見積もりを取り、費用とサービス内容を比較検討しましょう。
- 中古太陽光発電システム買取業者:
- まだ使用可能な太陽光パネルやパワコンなどは、中古市場で買い取ってくれる専門業者も存在します。
- ただし、FIT期間が終了したシステムの買取価格は、大幅に低くなることが予想されます。
選定のポイント:
- 撤去費用: 複数業者から見積もりを取り、相場を把握しましょう。足場設置費用や処分費、運搬費など、詳細な内訳を確認します。
- 適正な処理: 太陽光パネルは産業廃棄物として適切に処理される必要があります。リサイクルに対応しているか、許可を持つ業者かなどを確認します。
- 屋根の補修: 撤去後の屋根の補修工事についても、対応可能か、費用はどのくらいかを確認しましょう。
総合的な相談先
どの選択肢が良いか迷っている場合は、まずは以下の企業や団体に相談してみるのも良いでしょう。
- 地元の工務店やリフォーム会社: 住宅全体のリフォームやエネルギーに関する相談に乗ってくれる場合があります。
- エネルギーコンサルティング会社: 太陽光発電だけでなく、住宅全体のエネルギー最適化について専門的なアドバイスを提供してくれます。
- 各地域の地球温暖化対策推進センターや自治体の窓口: 補助金情報や、地域のエネルギー事業者について情報提供を行っています。
10年目以降の選択は、ご自身のライフスタイルや今後のエネルギーに対する考え方によって大きく変わります。複数の企業の情報を集め、見積もりを比較検討し、納得のいく選択をすることが重要です。